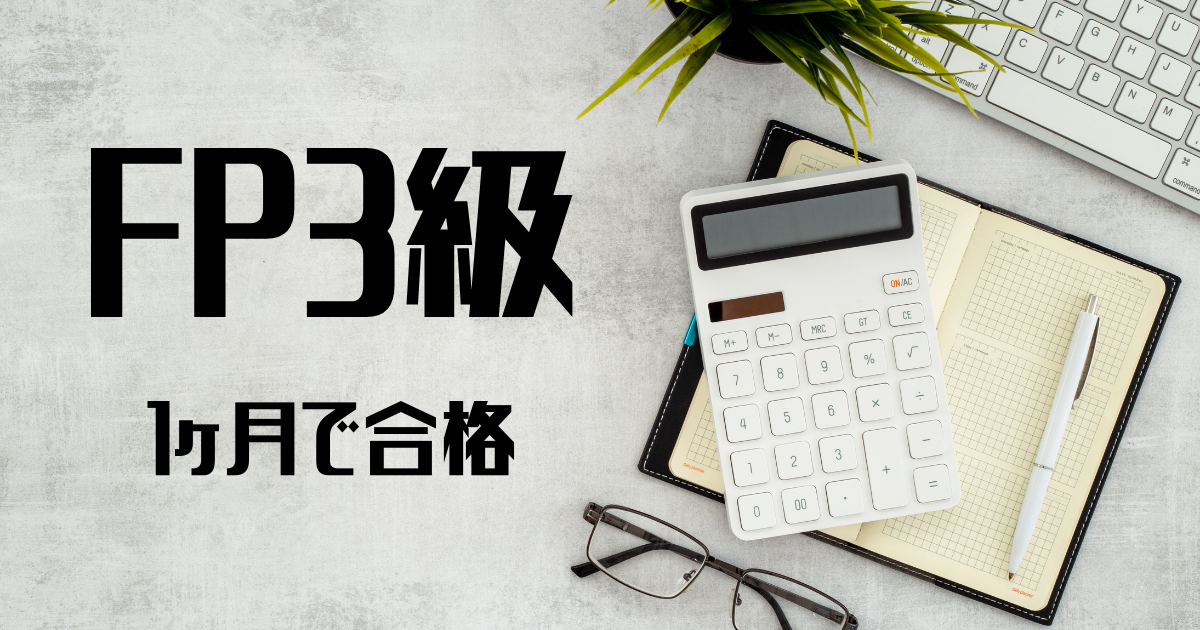ども、ごまです。今回は『FP3級合格方法』を紹介します。
FP3級に教材費2,000円、勉強期間1ヶ月(40時間+隙間時間)で合格しました。
使用した教材、効果があった勉強方法について書きます。あまりお金をかけずにFP3級にチャレンジしたい方は、参考にしてください。受験したのは、FP協会のCBT試験です。
使用した教材と費用
まとまった勉強時間が確保しずらい状況でしたので、動画学習をメインにすることにしました。
<教材一覧>
メインのインプットを「たぬぽんさんのYouTube動画」、「たぬぽんさん公式LINEの配布資料」を教科書代わりにしたので、こちらは無料です。僕は配布資料を持ち歩き用に紙に印刷したので、無印良品のA5サイズのルーズリーフ(100枚入り, 290円)とプリンターのインク代がかかりました。
みんなが欲しかった!シリーズは、ど定番書籍です。今回は「教科書」の方は購入せず、「問題集」だけを購入し、1,650円でした。
過去問道場は、広告表示が嫌でなければ無料で使えます。
<費用の合計>
プリンターのインク代を含めても、教材費は2,000円くらいで収まりました。CBT試験の受験料は、学科と実技、事務手数料を合わせて8,170円でした。受験料と教材費を合わせても、1万円ほどの出費でした。
勉強スケジュール
勉強期間を振り返って計算したところ、1ヶ月間、「40時間+隙間時間」で勉強をしていました。試験勉強をしたい時期と仕事の忙しい時期が重なったので、40時間の内訳は、仕事の日は就寝前30分〜1時間、休日はまとめて3時間程度が平均です。それ以外に、出勤時間などの隙間時間にも勉強をしました。
<スケジュール>
- たぬぽんさんYouTubeのFP3級勝組道場の動画を1本(1分野)視聴
- 問題集の動画視聴範囲の問題を解く(学科試験のみ)
- 間違えた問題はチェック・印刷した配布資料にポイントなどを書き込む
- 上の1〜3を、6分野分繰り返す [15時間]
- FP3級勝組道場の動画6本(全分野)を、1.5倍速で視聴する [4時間]
- 問題集(学科試験)の間違えた問題だけ、もう一度解く [3時間]
- 問題集の実技試験を全分野解く・復習 [6時間]
- 問題集についてくる総合問題(学科・実技)を解く・復習 [4時間]
- 学科・実技で苦手なところを過去問道場でやり込む [6時間]
- 問題集と総合問題で、チェックがついている問題を解く [2時間]
<隙間時間にやったこと>
基本的にこれだけです。試験まで余裕がある場合は、動画と問題集の周回回数を増やして確実に知識を定着した方が安心だと思います。
勉強スケジュールのポイントは、「早めに全分野を1周して苦手を把握すること」です。早期に全分野を一周するために、問題集は学科のみを先に一周しました。
個人的な感覚ですが、実技試験の問題の種類はこんなイメージです。
実技試験特有の解き方が必要なものは少ないので、先に学科試験の問題で苦手分野やインプット不足の内容を把握して潰していく方が効率的です。
隙間時間のポイントは、「動画を1.5倍速で聴きながら頭から抜けているポイントを探すこと」です。試験範囲は広いので、1つの分野の勉強に集中していると他の分野の知識がポロポロと抜けていってしまします。
おすすめの方法は、家でゆっくり学習する分野と違う分野のFP3級勝組道場の動画を隙間時間に聞き流し、「あれ?これなんだっけ?」と思ったらキーワードをメモしておいて、家で学習するときに復習する方法です。僕は通勤時間に動画を視聴しながらトラベラーズノートにキーワードをいくつかメモし、夜の勉強時間の一番初めにその内容を復習していました。その後に、もともと勉強しようとしていた範囲の勉強に取り組むので1日に最低でも2分野の内容を確認することができます。
勉強中に意識したこと
勉強中に意識していたのは、「自分または家族を制度に当てはめて考え、理解する」ことです。
社会保険、民間保険、税金、相続、、、様々な制度とその適用条件があり、その細かい数値なども試験範囲に含まれます。ここで、次のように覚えようとするのはおすすめしません。

XX制度の適用条件は、年齢が満65歳以上で・・・
YY制度は年齢制限はないけど年収が1000万円以下で・・・
これでは、問題を解くときにミスが起こりやすいです。なぜなら、どの制度も適用条件の文言だけを読むと似ているからです。
そこで僕がやったのは、「自分や自分の家族が対象者になったら・・・」という視点で考える方法です。

この給付制度は3つ条件があるけど、収入の条件は自分には当てはまらないから適用されないな。うーん、残念だなぁ。

あの時の父親の扶養控除額は、大学4年の僕の分が63万円、中1の弟のは0円だったのか。あと、母親の分は・・・
このように考えると、それぞれの制度に「自分の感想・感覚」が付与されて記憶に残りやすいです。どうしても自分や家族の条件に当てはまらないものもありますが、「もし10人兄弟だったら?」「もし祖父が80歳で現役並みの収入がある人だったら?」などと条件を仮定して考えるのも良いです。
やや不謹慎ではありますが、僕は相続分野の法定相続人について勉強したときに、家族を1人ずつ亡くなったと仮定して、どのように分配されるのかを考えました。父の兄弟が相続放棄していた場合、すでに家族の誰かが亡くなっていた場合なども追加条件として自分で問題を作りました。これのおかげで、相続分野は得意になったと感じています。知らない家族を想定するよりも、状況が掴みやすいのでおすすめの勉強法です。
[おまけ1] 短期集中でモチベーションを維持できた!
FP3級試験を調べていたとき、以下のことがわかりました。
調べていた当日が1月22日で、3月1日からCBT試験休止期間に入ります。この休止期間前のCBT試験を逃すと、受験日が少し先になってしまいます。
こう言う時に「あと2ヶ月もあるからゆっくり勉強しよ〜」と思ってしまうと、ブーストがかからない性格である僕は、

絶対にCBT試験休止期間に入る前に受験して合格だ!
という気持ちで、急ピッチで準備を進めました。
結果として、モチベーション高く1ヶ月間の勉強を進められました。思いがけず、短期集中で取り組むことになりましたが、FP3級の内容と難易度から短期集中型での挑戦が向いていたと思います。
もし、モチベーション維持が悩みであれば、先に1ヶ月後くらいの都合の良い日にCBT試験の申し込みをしてみるのもいいかもしれないです。そして申し込んだ後に、「さて、この期間で合格するにはどう戦略を組み立てようか?」と考えだすと止まらなくなります。
[おまけ2] たぬぽんさんの配布資料を印刷して勉強する際のおすすめ
僕と同じように、たぬぽんさんの配布資料を教科書にして勉強をしたいと考えている方におすすめの印刷方法は、「ルーズリーフ用紙の見開き1ページの左側だけに印刷する」方法です。
僕は無印のA5サイズのルーズリーフ用紙を使いましたが、お好みのサイズでよいと思います。
ルーズリーフに挟んでページを開いた時に、常に左側半分に資料の内容が印刷されていて、右側は何も印刷されていない状態です。これが一番勉強しやすいです。
問題集や過去問道場で問題を解いていくと、たぬぽんさんの動画で触れられていない内容やポイントとなるキーワードが出てくることがあります。自分で勉強を進めながら追加で抑えたいポイントがあれば、見開きの右側スペースに書き込んでいきました。また、資料ではあまり目立たないように書いてある内容だけど、問題を解くときに重要に感じるような内容があれば、自分でマーキングを追加して目立つようにしました。
こうして勉強を進めると、試験前には自分専用の教科書になっていました。書籍で教科書を購入しませんでしたが、僕はこれがベストなやり方でした。
まとめ
費用2,000円、1ヶ月の勉強でFP3級に合格するために必要なことをまとめます。

最後まで読んでいただきありがとうござます。参考になることがあれば嬉しいです。
FP3級の勉強を通して、お金のことを知るって大事だなぁと改めて考えるきっかけになりました。次は、日商簿記3級の勉強を始めます。